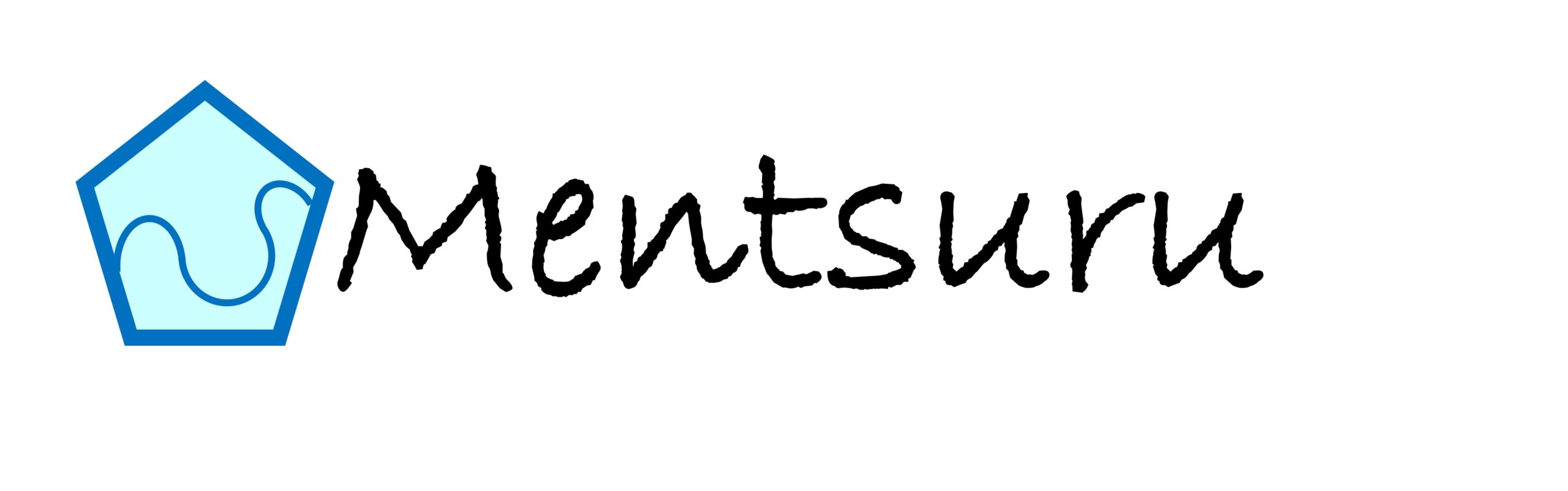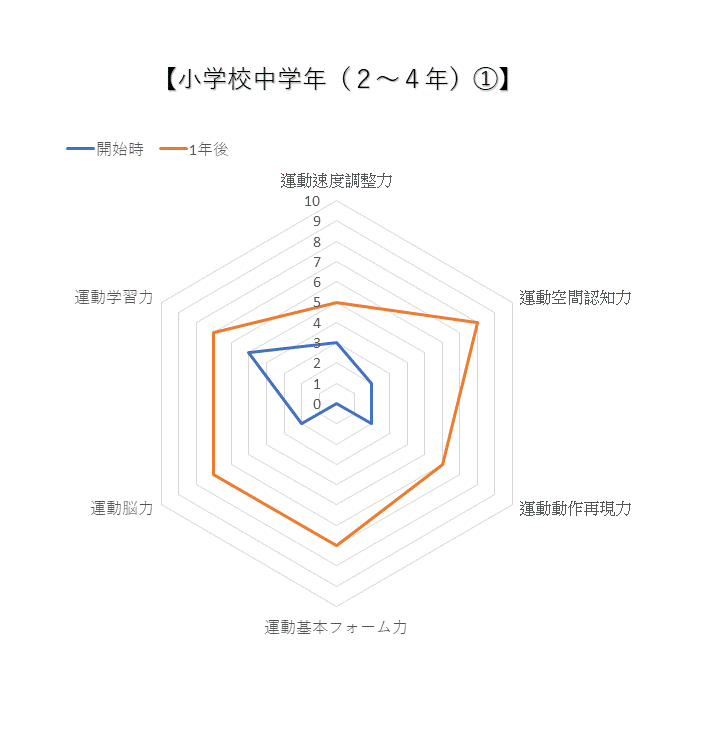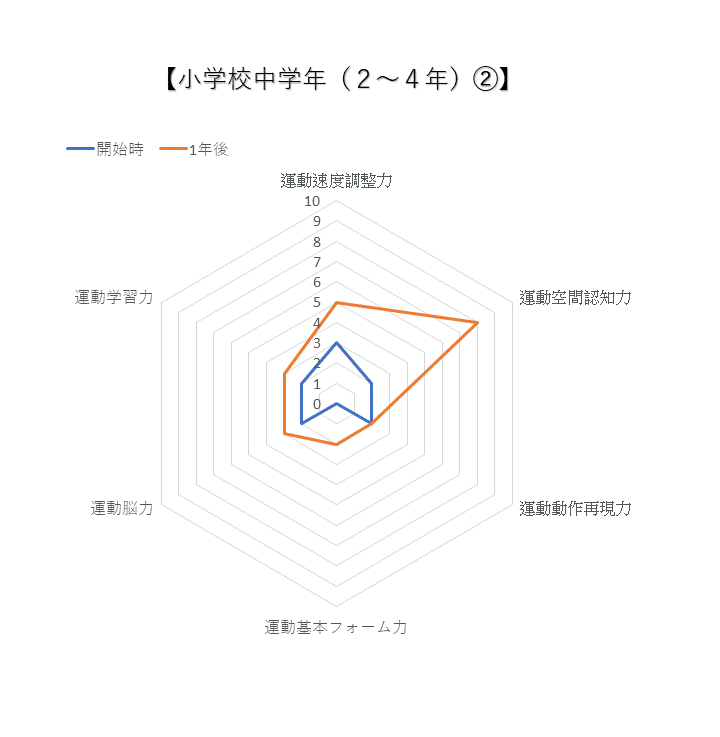どうもM2です。
多くのお子さんが、専門的なスポーツの教室に通い始める時期は小学校高学年だと思います。中学に上がると部活動がありますので、そのための準備であったり、遊びとしての運動から、競技としてのスポーツに意識が変化する時期でもあります。
今回の6アビリティーのグラフ表示では、ゴールデンエイジの最後の時期である小学校高学年についてです。この年齢までに、神経系の発達はほぼ100%完了していくと言われています。まさに、ここまでに遊びを通して体を動かす能力を高めていったものを、中学に入って運動部で特定のスポーツに活かしていくことになります。
では、グラフをみていきましょう。
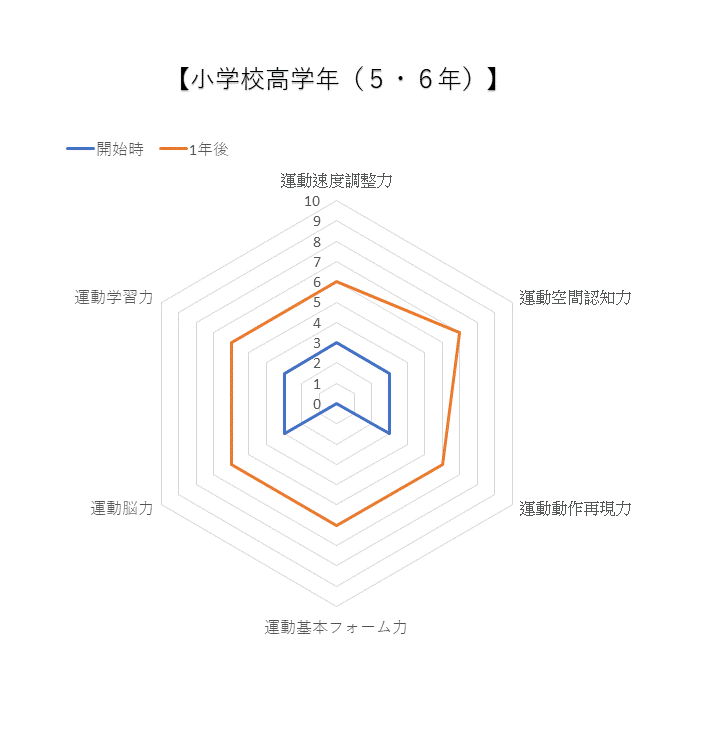
6アビリティーをそれぞれ10段階で評価しています。初めてのレッスンが開始時として青線。1年後にオレンジの線のように伸びていくと予測したグラフになります。
運動速度調整力
この時期になると個人差が大きくでてきます。性格や日常生活に大きな影響を受けていると推察しますが、おとなしい子だったり、普段から外遊びをしない子はなかなか伸びません。逆に、活発で勝負事が好きな子は、早く動くことはもともと得意でさらに伸びていきます。ただ、遅く動くことができないケースが多いのも特徴です。グラフの数値は平均をとったイメージになります。
運動空間認知力
小学校2~4年生の時と同様に、球出しのボールをラケットに当てることができない、コートに打ち返すことができない子は多くいます。日常的な遊びで大きなボールには慣れてる子供たちでも、4センチのボールを15センチ幅程度のラケットに当てるのは最初は難しいのです。しかし、ボールつきをしたり「ボールが飛んでいく場所は、ラケットの角度とラケットの動く方向、力加減で決まる」を理解して体を動かし始めると、ほぼ例外なくこの能力は伸びていきます。
運動動作再現力
準備体操をしている様子で、この能力の高さはある程度判断ができます。コーチの動きを正確に真似ができる子は、卓球をさせても見様見真似でできてしまいます。これは、これまでの生活の中で運動学習力や運動脳力に多く影響されていると考えています。こちから見ているとはっきり分かるのですが、できていない子は、こちらの動きをよく見ていないのです。「見て真似よう」という意思が目線で分かります。見ていないのであれば真似ることはできないです。単純に運動脳力が低いと思われるかもしれませんが、これまでの生活の蓄積がこの能力を生み出しています。そして、大人でも同様ですが、特定の動きが苦手というケースも多くあります。例えば、バックハンドはできるが、フォアハンドは全く上手くいかない。または、その逆のパターン。これは肩の関節の柔軟性にも影響していると思いますが、個々人によって特徴があります。コーチ側としては悩ましいのですが、多くのケースではいろいろな肩の運動を繰り返していくことでできるようになる子が多くいます。
運動基本フォーム力
他の年代と全く同じですが、初めの数値は0です。ただし、学童や学校のクラブ活動(週1回の授業)で卓球をしている子もいるため、何となく基本フォームを習ったり真似たりしている子もいます。テニスを習っていた子もフォアハンドロングは、それとなくラケットがおでこの方向に動かします。この時期はゴールデンエイジの後半となり、多くの場合は大人よりも早く基本フォームを習得できます。
運動脳力
小学校2~4年生の時から継続して通っている子のなかで、悪ふざけをして練習に集中できない子が徐々にそういった行動をしなくなっていく事が多く、その変化が大変興味深いです。活発にしゃべりかけてきたり、メンバーとふざけあって走り回ったりすることが少なくなり、コーチとのコミュニケーションも恥しがる様子は、まさに思春期に入っていくことを実感します。そして、考える力も高まり「なぜ?」の質問にも、正しく回答してきます。ほんとに小さい声で(笑)。悪ふざけをせず、理解もしながら体を動かすので、当然ですが技術の習得スピードも加速していきます。一般的には体の成長があるから当然と思われるかもしれませんが、運動脳力の影響はかなり大きいといえるでしょう。
運動学習力
小学6年生になると、多くの子が運動学習力を伸ばしてきます。上述したように、遊びとしての運動からスポーツとしての意識が高まるこの時期は、上達していきたいと思う姿勢のままに技術の習得をしていきます。勉強は苦痛を伴いますが、スポーツは多少ハードな練習でも楽しいと感じることができます。学習という意味では同じなので、ここに教育面でのスポーツの良さがあると私は考えています。
私が指導してきた子供たちの多くに、中学に進学した段階で卓球部ではなく文化部に所属するケースがあります。競技的な卓球教室では珍しいことだと思いますが、とても良いことだと思っています。そもそも、卓球は他のスポーツと比較して、簡単で安全なため運動が苦手でおとなしい子でも始めやすいものだと感じます。なので、サッカーやラグビーなどの競技者からは、正直馬鹿にされている存在であるのは確かです。「運動はしたい。でも目立ちたがりやで活発な人達とは一緒にやるのは嫌」と感じるなら、卓球は最適です(笑)。なので、文化部に所属しつつも、私のところで週に1回程度でもいいから体を動かし、徐々に思った通りに体が動いていくことを楽しむ・・。本当に素晴らしいことを提供していると自負しています。