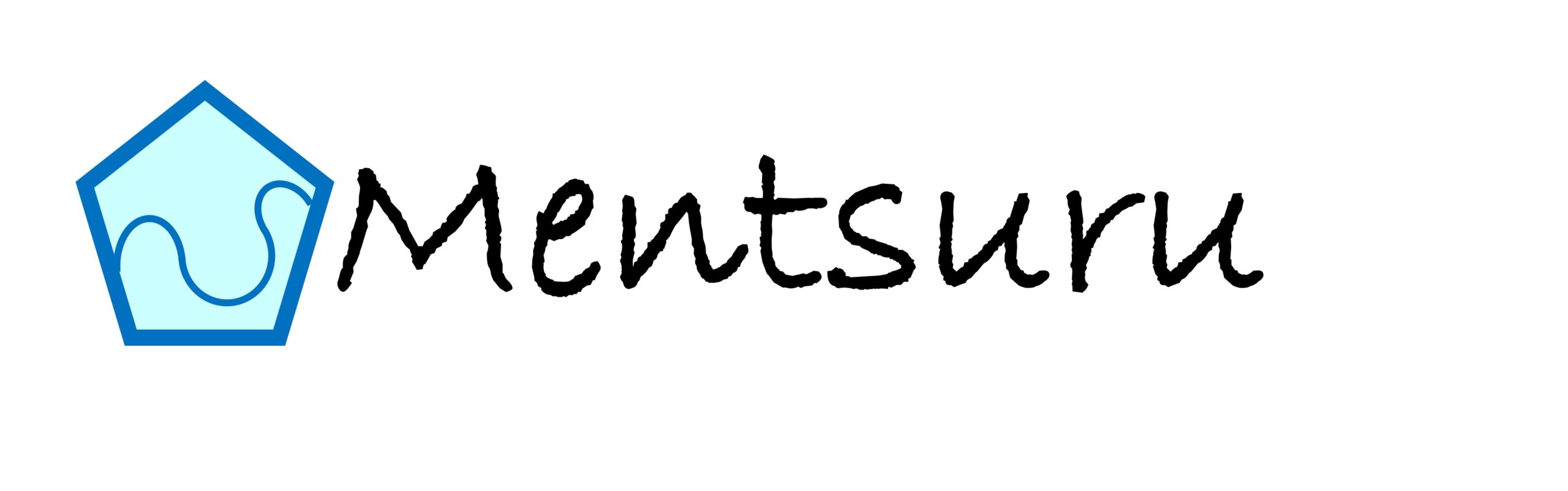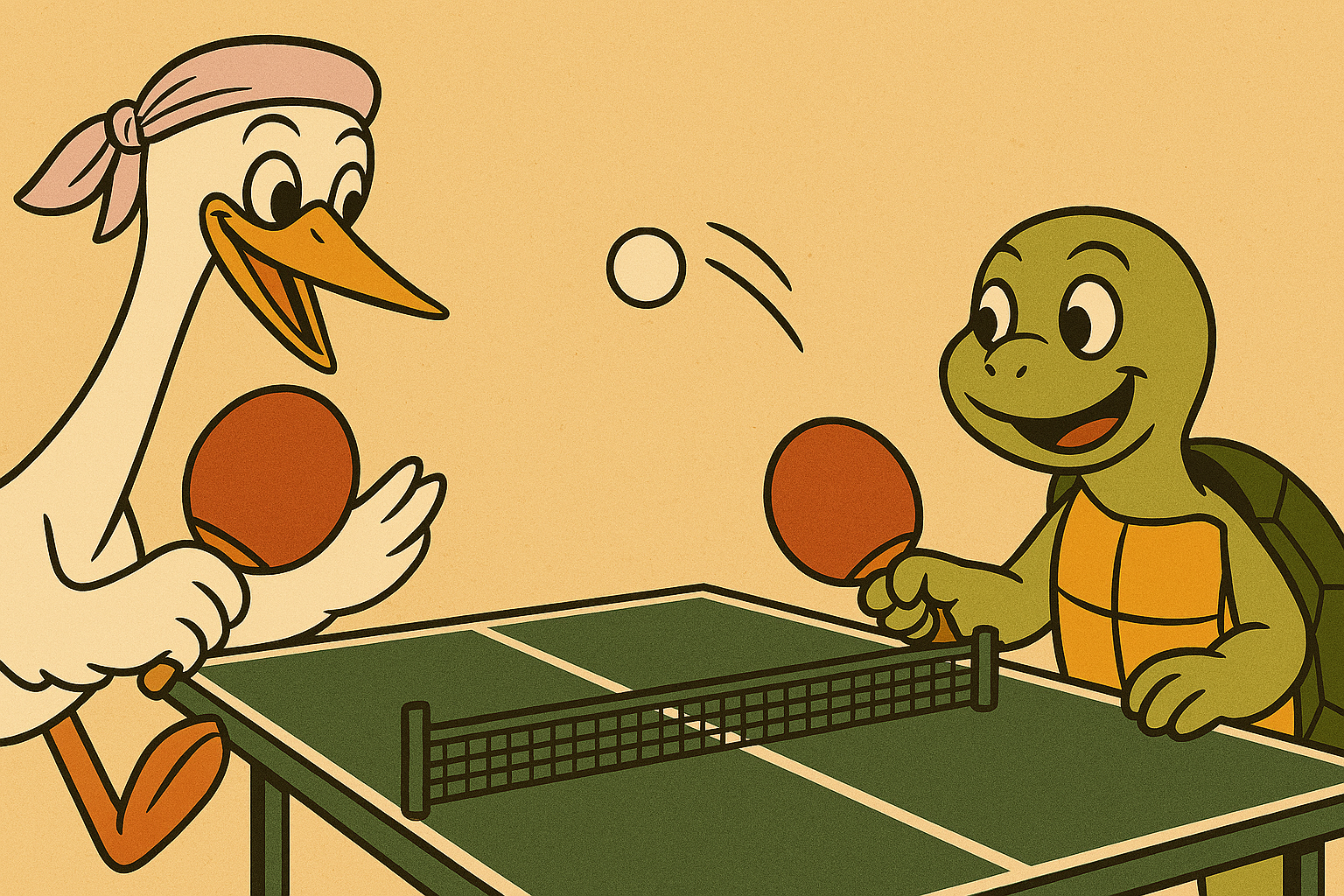はじめまして。メンツルブログ(通称:メンブロ)管理人のMentsuruです。
私は卓球指導者として多くの卓球初心者や未経験のコーチをしてきました。その中で培った経験や指導方法を論理的に正しく伝えていきたいと考えるようになりました。
スポーツは教える側にとても高いスキルが求められますが、学ぶことや充実感も得られます。まだまだ私も半人前。このブログで情報発信しながら、これからも皆さんと一緒に学んでいきたいと思います!!
このブログでは、これから卓球指導者になる方や、すでに指導者で指導方法に悩んでいる方に、卓球を上達させるために必要な知識や情報を詳しく解説していきます。

スポーツを指導するために必要な知識を誰にでも分かりやすく解説していくよ。

Mentsuru
メンブロの管理人。卓球指導者を指導するエキスパート。
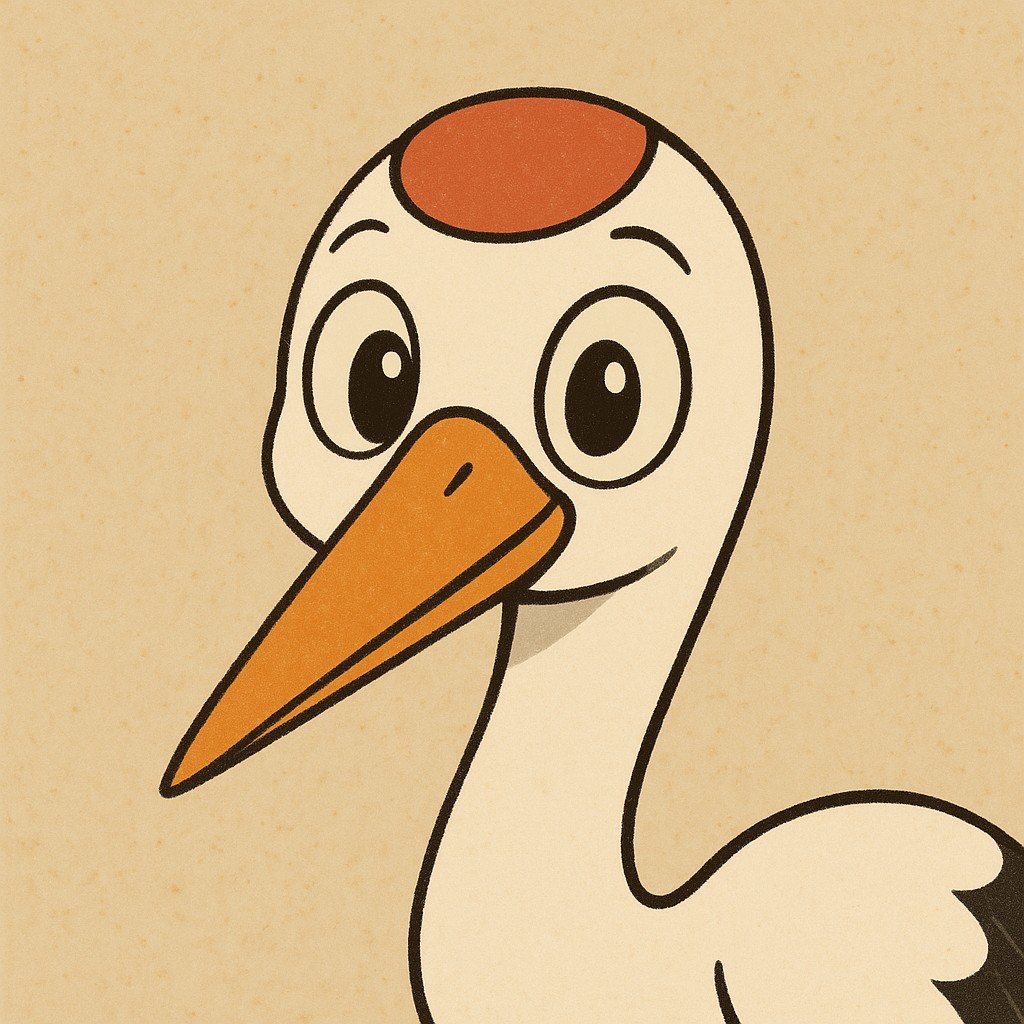
鶴介(つるすけ)
卓球指導歴1年目。もっと良い指導になりたいと奮闘中。

亀吉(かめきち)
卓球経験ゼロ。卓球指導になるための知識を勉強中。
メンブロの登場人物(人?)は3名。卓球のグッドコーチを目指す『鶴介』『亀吉』とともに学んでいきましょう!!
- グッドコーチとは?
- グッドコーチの7の提言
- 上達が遅い人はやる気がない?
- 6アビリティーとは
- 6アビリティー
- 動作表現力
- 空間認知力
- 動作表現力
- 基本フォーム力
- 運動脳力
- 運動学習力
「グッドコーチ」とは?
まずは、文部科学省に掲載されている資料から、国としてグッドコーチをどのようにとらえているかみていきましょう。
スポーツ指導者(コーチ)は、スポーツ科学やスポーツ医・科学の知識・技能を身に付けていることはもとより、スポーツの意義と価値を理解した上で、スポーツとは何か、何のためにスポーツ指導をしているのかを常に自分自身に問いかけ、成
長し続ける必要がある。
「グッドコーチに求められる資質能力」は、プレーヤーやスポーツの未来に責任を負う上で幹となる思考・判断を中心に、実際のコーチングを適切な方法で表現し良好な関係を築くための態度・行動、あらゆるスポーツコーチングの場面で必要となる知識・技能(共通)と個々のコーチング現場別(競技別、年代別、レベル別、障害の有無など)において必要となる知識・技能(専門)により形成される。

やや漠然とした表現だけど、スポーツ指導者は、自分自身が高い技術力をもつだけではなく、日々勉強し習う者への責任があることを伝えているよ。
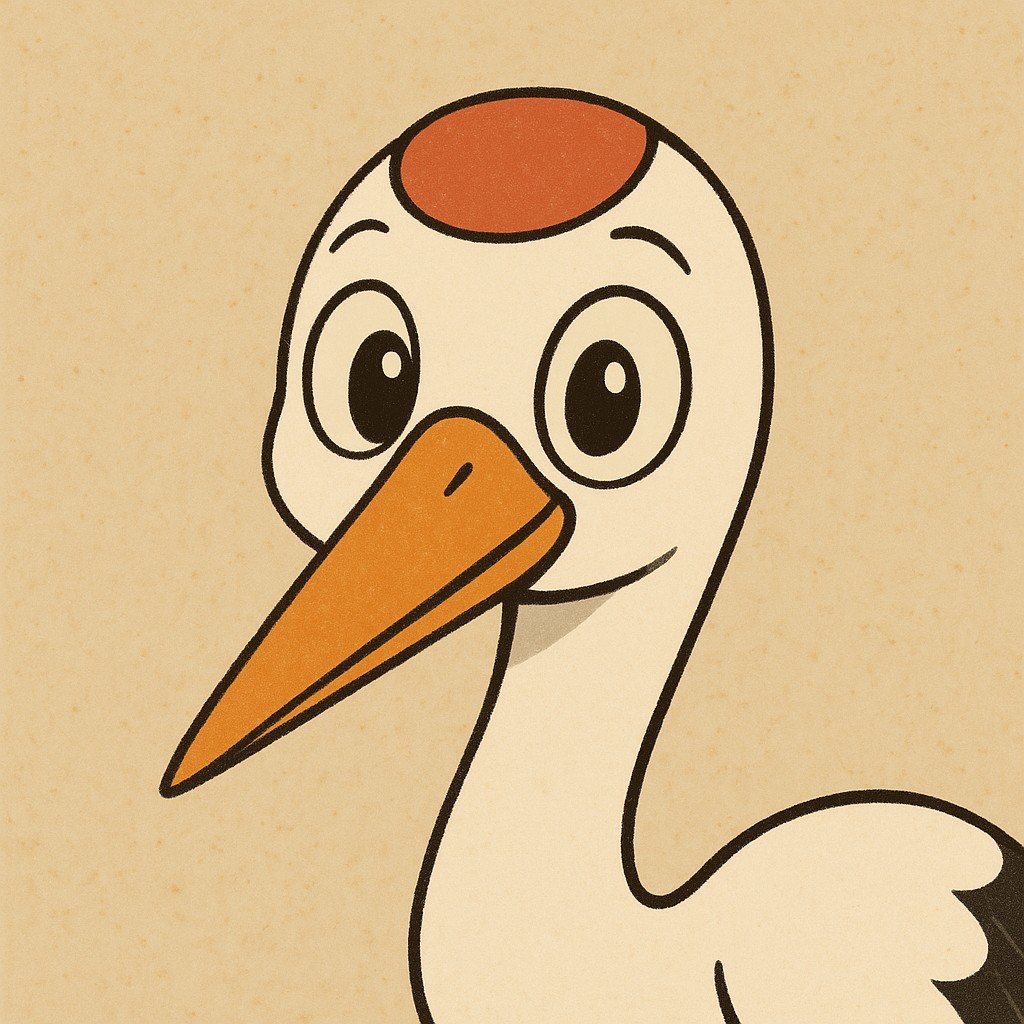
グッドコーチを目指すのは、様々な知識が必要ってことですね。他には、どんなことがあるんですか?
グッドコーチは、知識・技術の習得はもちろん、人間力を養うことも重要とされている。以下がグッドコーチに必要とされる能力。
・人間力(思考・判断):自分自身のコーチングを形づくる中心にあるもの
・人間力(態度・行動):プレーヤーや社会との良好な関係を築くために必要な資質能力
・知識・技能(スポーツ知識・技能):スポーツ指導を行ううえで必要となるスポーツ科学の知識・技能

う~~ん。ただ卓球の技術と知識さえあればいいから卓球の勉強しよって思ってたのに、「人間力」って、、、。グッドコーチ像がなんだかスゲー人って感じです。

その通り!
〇〇競技のコーチです。と言うだけなら簡単。
それ相応の人間であることが求められるし、習う側以上に努力ができなければならないということだね。
でも、『競技において高い成績をおさめた者』とは一言も書いてないんだ。
良い結果を残せた者が良い指導ができるのではなく、正しい知識を身に着ければ誰でも「グッドコーチ」になる可能性があるということだね。
グッドコーチの7の提言
この資料には、グッドコーチに求める7つの提言として、より具体的な内容を示しています。
1.暴力やあらゆるハラスメントの根絶に全力を尽くしましょう。
暴力やハラスメントを行使するコーチングからは、グッドプレーヤーは決して生まれないことを深く自覚するとともに、コ ーチング技術やスポーツ医・科学に立脚したスポーツ指導を実践することを決意し、スポーツの現場における暴力やあらゆるハラスメントの根絶に全力を尽くすことが必要です。
2.自らの「人間力」を高めましょう。
コーチングが社会的活動であることを常に自覚し、自己をコントロールしながらプレーヤーの成長をサポートするため、グッドコーチに求められるリーダーシップ、コミュニケーションスキル、論理的思考力、規範意識、忍耐力、克己心等の「人間力」を高めることが必要です。
3.常に学び続けましょう。
自らの経験だけに基づいたコーチングから脱却し、国内外のスポーツを取り巻く環境に対応した効果的なコーチングを実践するため、最新の指導内容や指導法の習得に努め、競技横断的な知識・技能や、例えば、国際コーチング・エクセレンス評議会(ICCE)等におけるコーチングの国際的な情報を収集し、常に学び続けることが必要です。
4.プレーヤーのことを最優先に考えましょう。
プレーヤーの人格及びニーズや資質を尊重し、相互の信頼関係を築き、常に効果的なコミュニケーションにより、スポーツの価値や目的、トレーニング効果等についての共通認識の下、公平なコーチングを行うことが必要です。
5.自立したプレーヤーを育てましょう。
スポーツは、プレーヤーが年齢、性別、障害の有無に関わらず、その適性及び健康状態に応じて、安全に自主的かつ自律的に実践するものであることを自覚し、自ら考え、自ら工夫する、自立したプレーヤーとして育成することが必要です。
6.社会に開かれたコーチングに努めましょう。
コーチング環境を改善・充実するため、プレーヤーを取り巻くコーチ、家族、マネジャー、トレーナー、医師、教員等の様々な関係者(アントラージュ)と課題を共有し、社会に開かれたコーチングを行うことが必要です。
7.コーチの社会的信頼を高めましょう。
新しい時代にふさわしい、正しいコーチングを実践することを通して、スポーツそのものの価値やインテグリティ(高潔性)を高めるとともに、スポーツを通じて社会に貢献する人材を継続して育成・輩出することにより、コーチの社会的な信頼を高めることが必要です。
国が示す「グッドコーチ」について紹介してきました。
そのうえで、具体的にプレーヤーをどのように指導していけばよいのか?
その一つの答えとして、私は「プレーヤーを6つの能力(アビリティー)で評価しながら指導する」6アビリティー理論を提唱しています。
上達が遅い人はやる気がない?
卓球の指導をしていると、同じ指導をしているのに簡単にできてしまう方と、なかなかできない方がいるということに気がつくはずです。
簡単にできてしまう方は、センスがいいとか、やる気があるとか、教えることが簡単に思えます。
逆に、なかなかできな方に対しては、「不器用」とか、「やる気がない」とネガティブな感情さえ抱くことさえあります。

小学生の時に体育が得意な人は「運動神経がいい」って、モテモテだったなぁ

運動が得意ということカッコいいと感じるし、逆に苦手な子にとっては苦痛に感じることもあるだろうね。
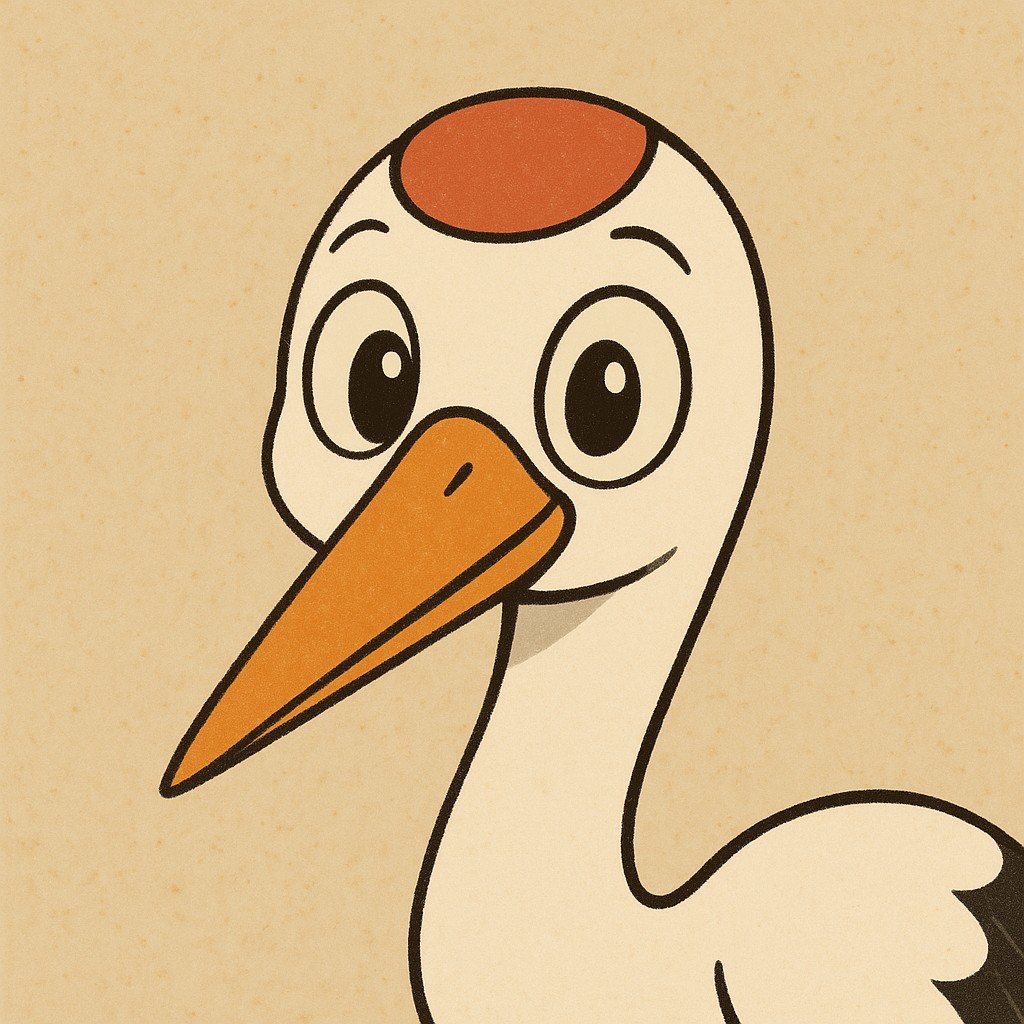
でも、なんで皆おなじように先生から習っているのに、運動がすぐできてしまう子となかなできない子がいるんですかね??できない子が単に「やる気がないから」と考えては可哀そうな気がします。

それは努力と根性が足りなんでしょう?気合がたりないんですよ気合が!!

それはどうだろう?
例えば、体育で逆上がりがずっとできない子が、毎日必死に一人で練習を繰り返しているとしよう。その隣で習ってもいない子が空中逆上がりでクルクル回りながら遊んでいる。
できない子はやる気がなくて、できる子がやる気があると、本当にそう考えるかな?
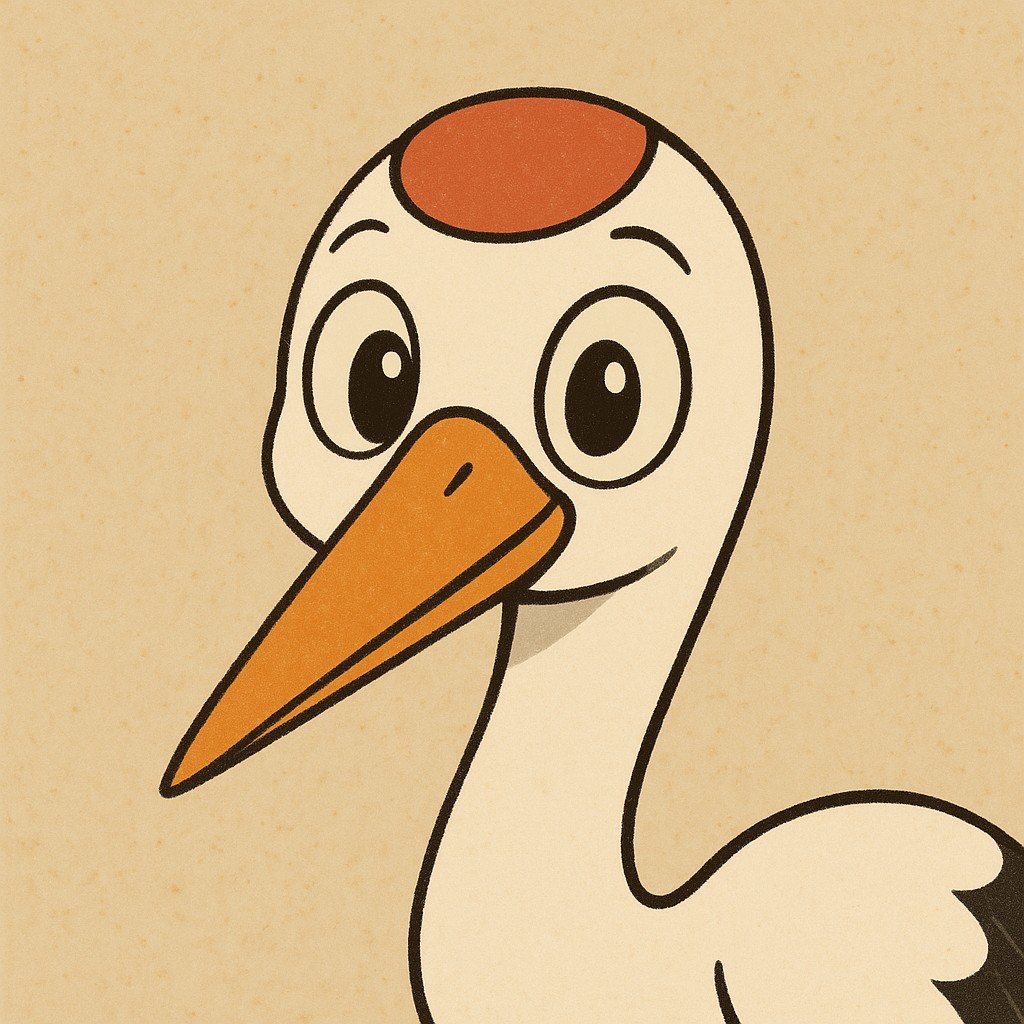
やる気が無くてできないこともあるかもしれないけど、それは運動神経が良いからじゃないですか?

では運動神経がいいって何だろう?さっきの例で、できなかった子が逆上がりに成功して、その体験から体操を初めてインターハイにする選手に出場することだってある。
逆に、トップアスリートでも自身の競技以外は全然できないこともあるんだよ。空中逆上がりができた子は、別にやる気があっても無くてもできただろうしね。
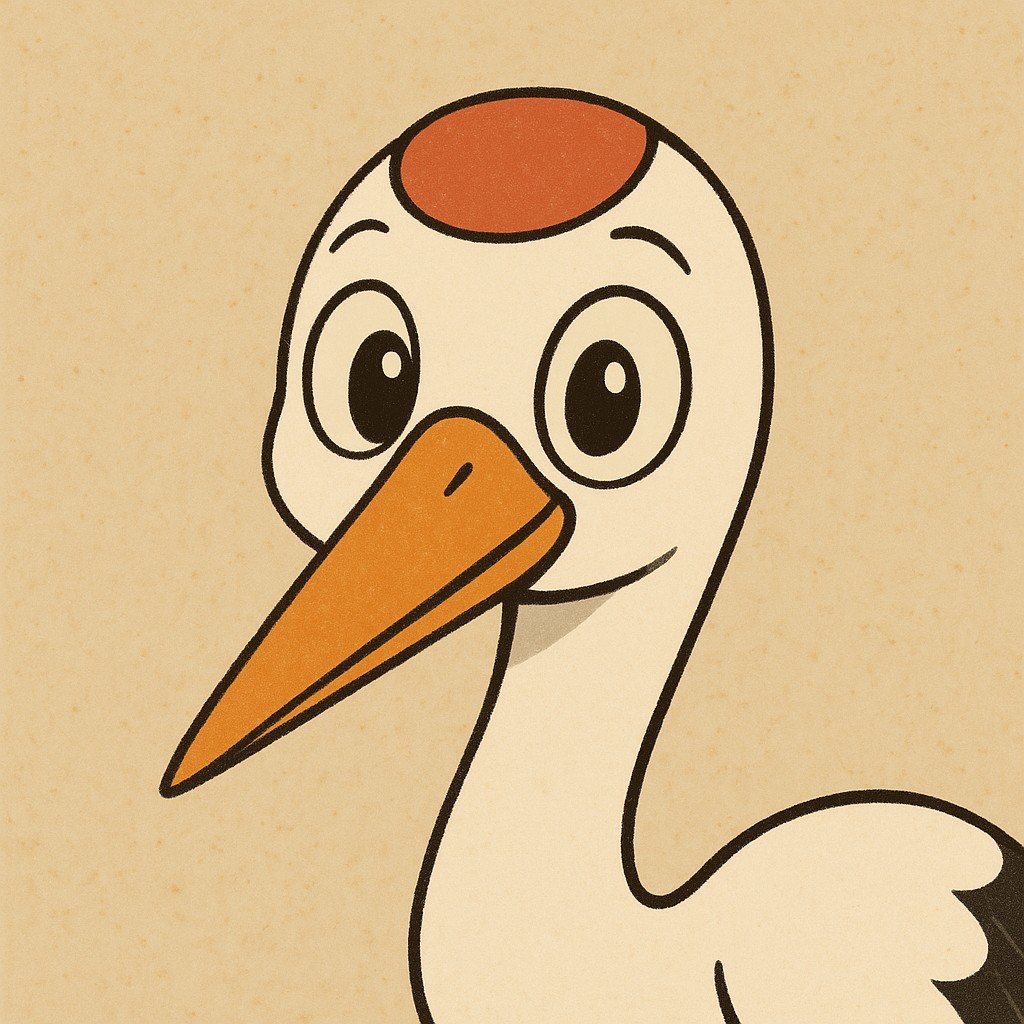
たしかに運動神経がいいからとか、やる気があるからと一つの理由だけで判断することはできないですね。

いや、最後はやる気っす。気合と根性です

一昔前の日本のスポーツでは当たり前だったスポ根も当然必要だとは思います。しかし、運動の上達が早い・遅いことが、やる気のみで判断するのはやや無理がありますよね?
6アビリティーとは?
私は卓球の指導を10年以上行い、どうして同じ指導をしているのに上手くなる人と、そうではない人がいるのか??その答えを探し続けてきました。
そして、何百名という卓球未経験者の方々を指導するなかで、卓球が上達するには能力が必要で、それは6つの項目に分類することができることに気が付きました。
そこにはやる気も当然入ってきますし、『運動神経がいい』『センスがある』といった言葉についても、6つの能力を用いて、なぜそう感じるのかを具体的な指標をもって表すこともできます。
逆に、「できない」には、6つの能力の何かが不足していて、その能力を意識的に伸ばすことによって、より早くプレーヤーを上達させていくこともできるようになりました。
これが、6アビリティー(Ability)理論です。
そして、この考え方は卓球だけではなく、ほぼ全ての競技にも当てはまると考えています。
卓球上達に必要な能力
皆さんは、スポーツ指導を行う中で、『指導通りにやってくれれば上手くいくのに』と感じたことはありませんか?
私も数えきれないほどこの場面に出会っています。
逆に、『こうしたらいいんだ』と言われても、「分かってるけど、それができません」と感じた経験もあるはずです。
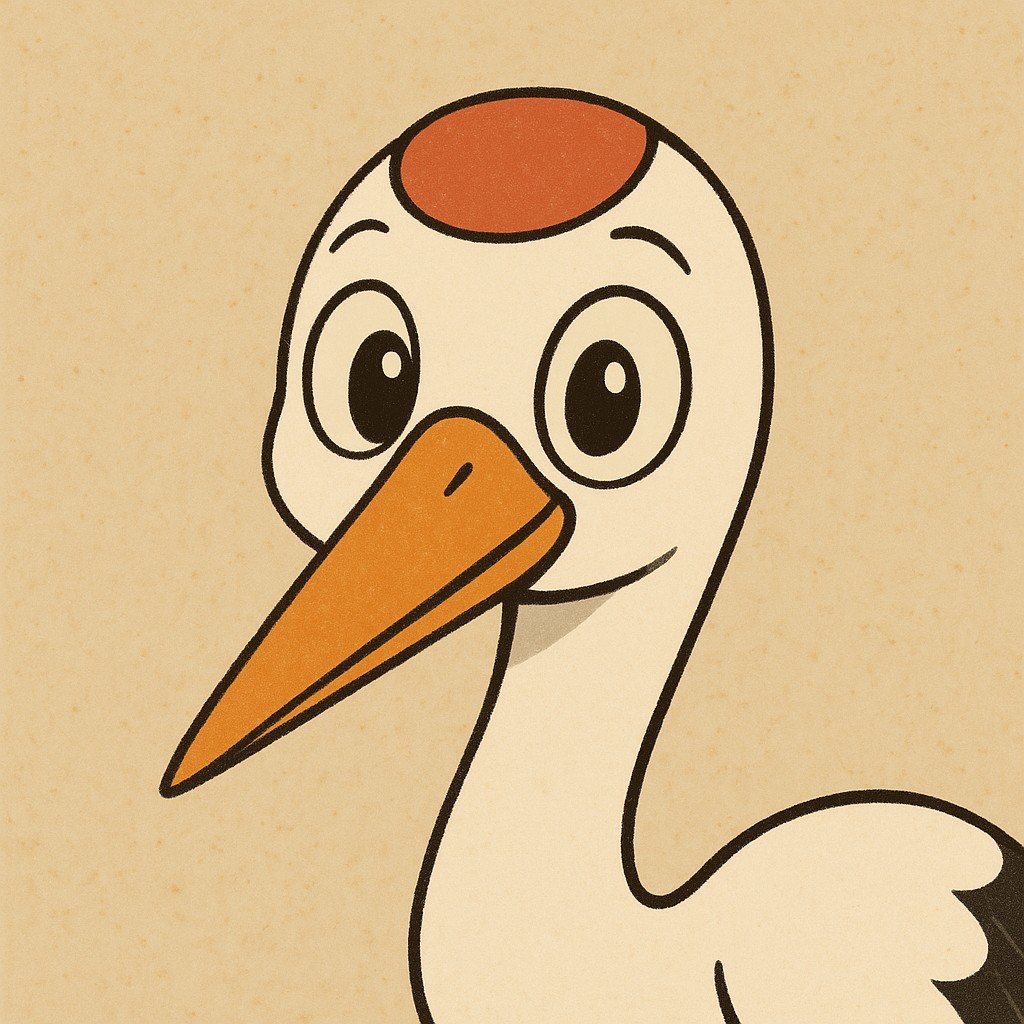
今まで技術をただ教えることに集中して、上手くいけば教え方が良かったし、上手くいかない時は自分の指導方法が良くなかったと思っていました。

僕のコーチは、「言われたとおりにやれ!」って怒ってたなぁ。そんな難しいこと言われても、、、といつも思ってました。

プレーヤーが指導通りに上手くできない時、指導者がよく使う言葉に「不器用」「やる気がない」があるよね。これを他の言葉に置き換えてみよう。
不器用 ⇒ プレーヤーが思っている通りに動いてくれない『体』
やる気がない ⇒ 指導者が思っている通りにに考えていない『脳』
プレーヤーが指導のアドバイス通りにやらない時に、プレーヤーは『分かっているけど、できないの!』と感じている場合が殆どです。このできない理由には『体』と『脳』にあると考えています。
鶴介の話でいうと、指導法自体は理論的に正しいことを言っていたのかもしれません。しかし、その動き自体をプレーヤーが行えなければ「指導法は正しいが、それを本人の体が行えてない」状態だったと言えます。
亀吉の経験談は、ややコーチに問題があるかもしれませんが、ネガティブな感情が芽生えて、実はコーチの指示を正確に理解していないだけの可能性が高いのです。指導者のイメージと亀吉がやろうとしていることが違っていたら、それは上手くいくわけがありません。

プレーヤーが指導通りに上手くできた時というのは、プレーヤーの『脳』が正しく理解をして、プレーヤー自身が思った通りに『体』が動かせた結果ということなんだ。
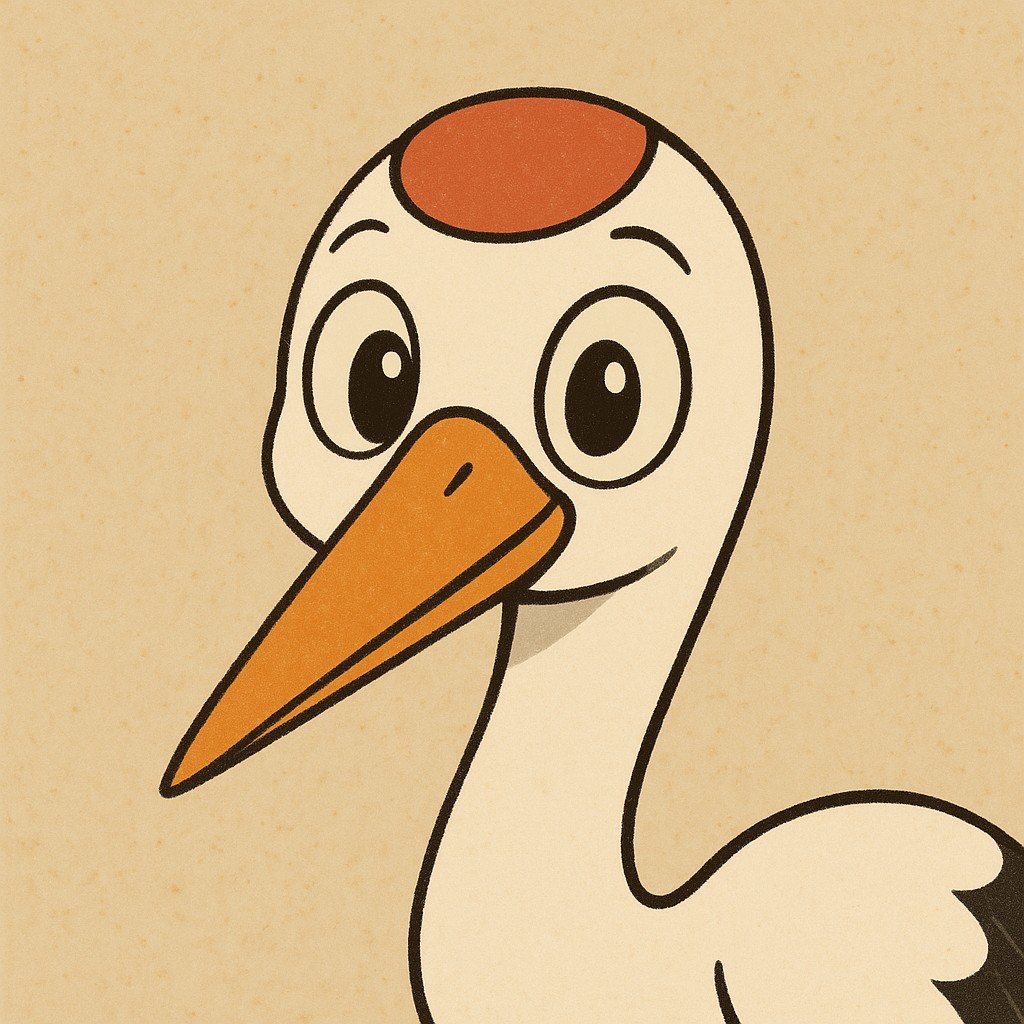
なるほど!この『脳』『体』の2つの分類から、さらに6つの能力に細分化して考えるということなんですね。

その通り!!指導者は、ただ「やる気が無い」とか一つの側面だけでなくて多方面からプレーヤーが「できない」理由を探せるし、課題解決へのアプローチの選択肢が広がるということなんだ。

6アビリティー『6つの能力』
ここからは6つの能力を具体的に解説していきましょう。
ちなみに、それぞれを私の造語です。
学術的な用語で説明するよりも、一般的な言葉からイメージし易いほうが良いと思ったこととや、当てはまる言葉が見つからず造語で表現することになった理由です。
体
- 速度調整力
- 空間認知力
- 動作表現力
- 基本フォーム力
脳
- 運動学習力
- 運動脳力
6つの能力は、目で見て分かる動作に関することで『体」に4つ。本人の頭の中で起こっていて指導者が見ることができない『脳』に2つ分類されます。
それでは、各項目について解説していきましょう。
1.速度調整力

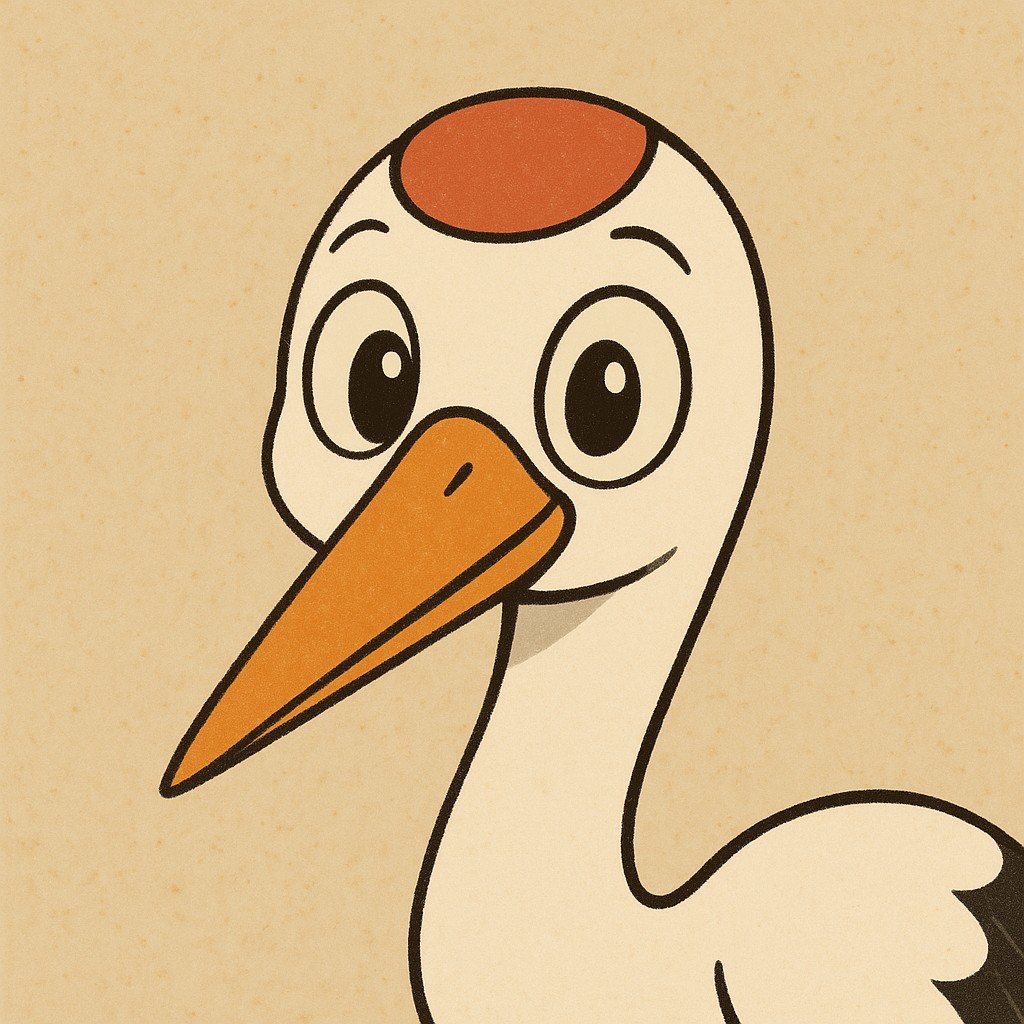
この能力の意味は分かります。力強く早い動きができないと殆どのスポーツでは勝っていけないですからね。

正解!。でもそれだけじゃないいよ。
スポーツで重要な能力の一つが「速く動くこと」。タイムを競う競技では結果に直結し、野球やサッカーでも体の一部を速く動かす場面が多くあります。卓球でも強いボールを打つために速さは不可欠です。
しかし、卓球の技術が上達していくと「遅く動かす」能力も同様に重要だと気づきます。例えば卓球のブロックのように、ラケットを振らずに返球する場面では、意図的に動きを抑える必要があります。これは他の競技でも同様な技術が多くあります。サッカーであればロングパスをトラップしたり、バレーボールでスパイクと見せかけてフェイントでゆっくりなボールコートの空いたスペースに落とす時などがあります。
つまり、速さだけでなく、どの場面でどの部位をどの速度で動かすかを正確に制御する「運動速度調整能力」が重要なのです。

そういうことかぁ。ただ強くラケット振れって勝てるわけじゃないってことですね。

そうなんだ。特に対人球技スポーツでは、お互いに攻めと守りを繰り返しているから見ごたえのあるラリーになる。全て全力で打ち合うことは難しくて、レベルが上がるほどこの速さと遅さをスイッチする運動能力が重要なんだ。
2.空間認知力

う~~んん。空間認知力なんて聞いたことないなぁ。いったい何ですか??

言葉は初めてでも、誰もがこの能力を使って生活をしているよ。
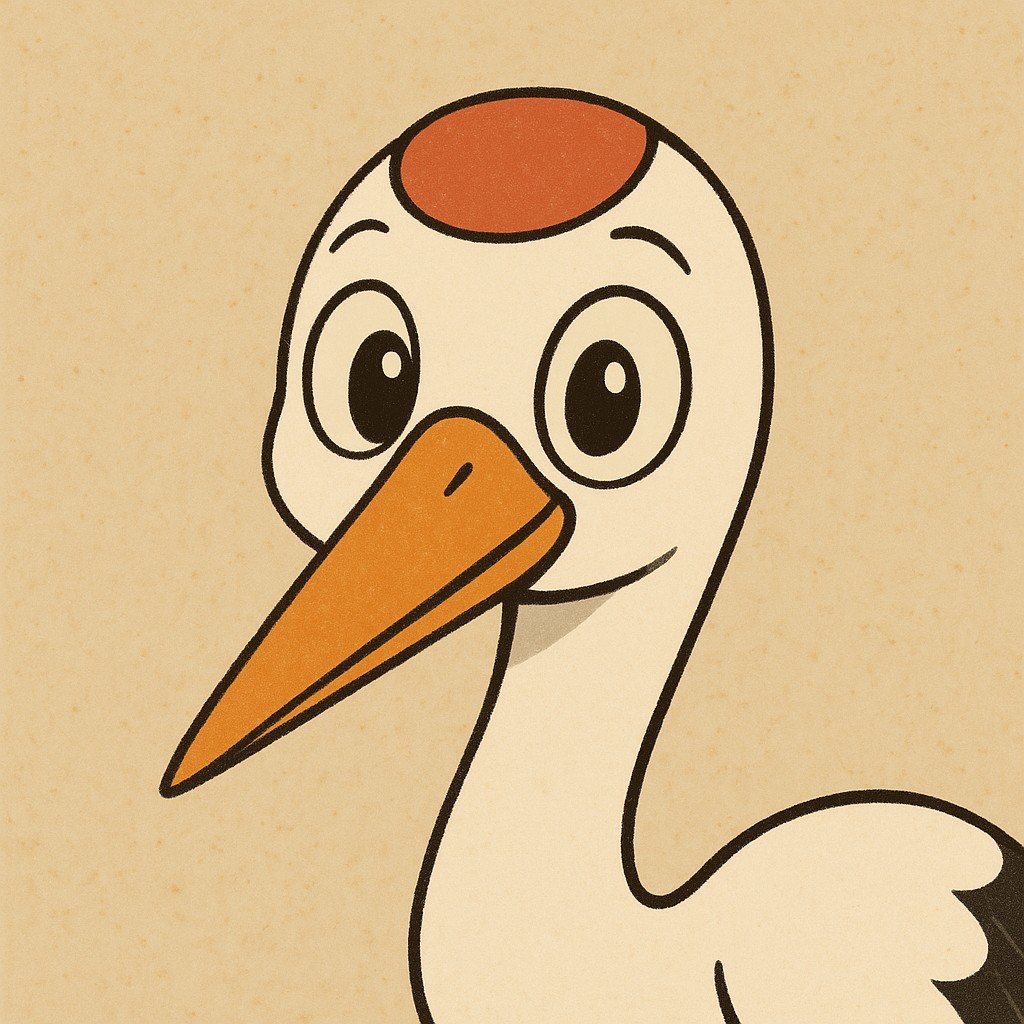
え?普段からこれを使っている??空間を認知するって何ですか?
皆さんは、普段生活をしていて物体との距離を意識することはありますか?
もし、「無い」と思った方。歩いていて人とすれ違う時に避けて通ろうとしませんか?これはまさに空間を認知しています。
例えば、避けようと思って横に動こうとすることを30メートル手前でやったら「正しく空間を認知できていない」と言えます。このままだとぶつかってしまうと感じるのは、おそらく2,3メートル手間です。これは「この距離で、この速度で歩いていたら、あと数秒でぶつかる」と勝手に脳が判断をしたからです。
もし、この能力が無かったとしたら、しょっちゅう人とぶつかるか、意味もなく右左に動きながら歩くしかありません。

他にも、水たまりを飛び越えようとするときに「これなら飛び越えられる」と思うよね。これは過去の経験や自分の体力を脳が『カン』によって無意識に判断している。

ありますね~~~。それでちょっと足りなくて「バシャ」って足びっちょびちょみたいな。
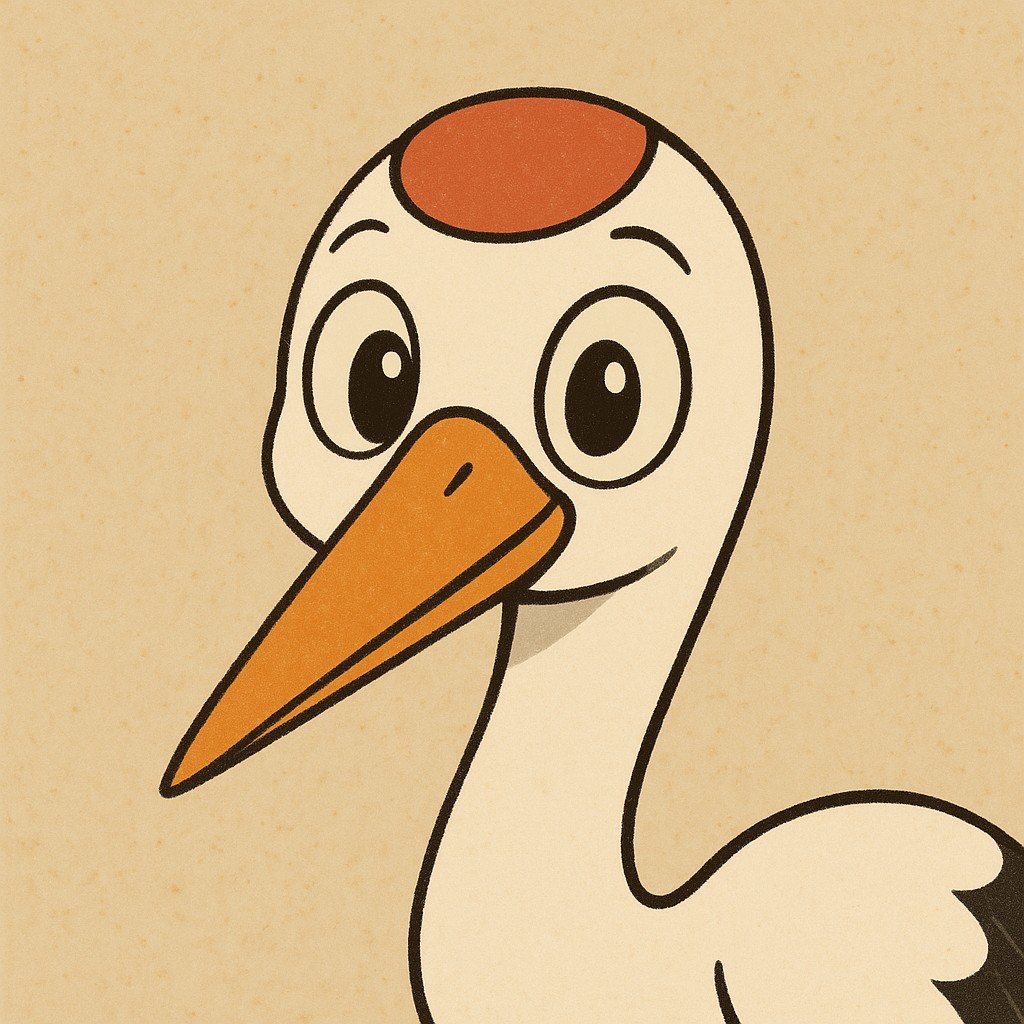
そうか。それが「正しく空間を認知できていない」ってことか。
野球のフライをキャッチすること。バトミントンで山なりに来たシャトルをスマッシュすること。
自分の頭よりも高い位置にある物体が、どれくらいの距離で、どれくらいの時間で、どこに落ちてくるのかを経験者は性格に判断しながらプレーしています。
これが運動空間認知力です。
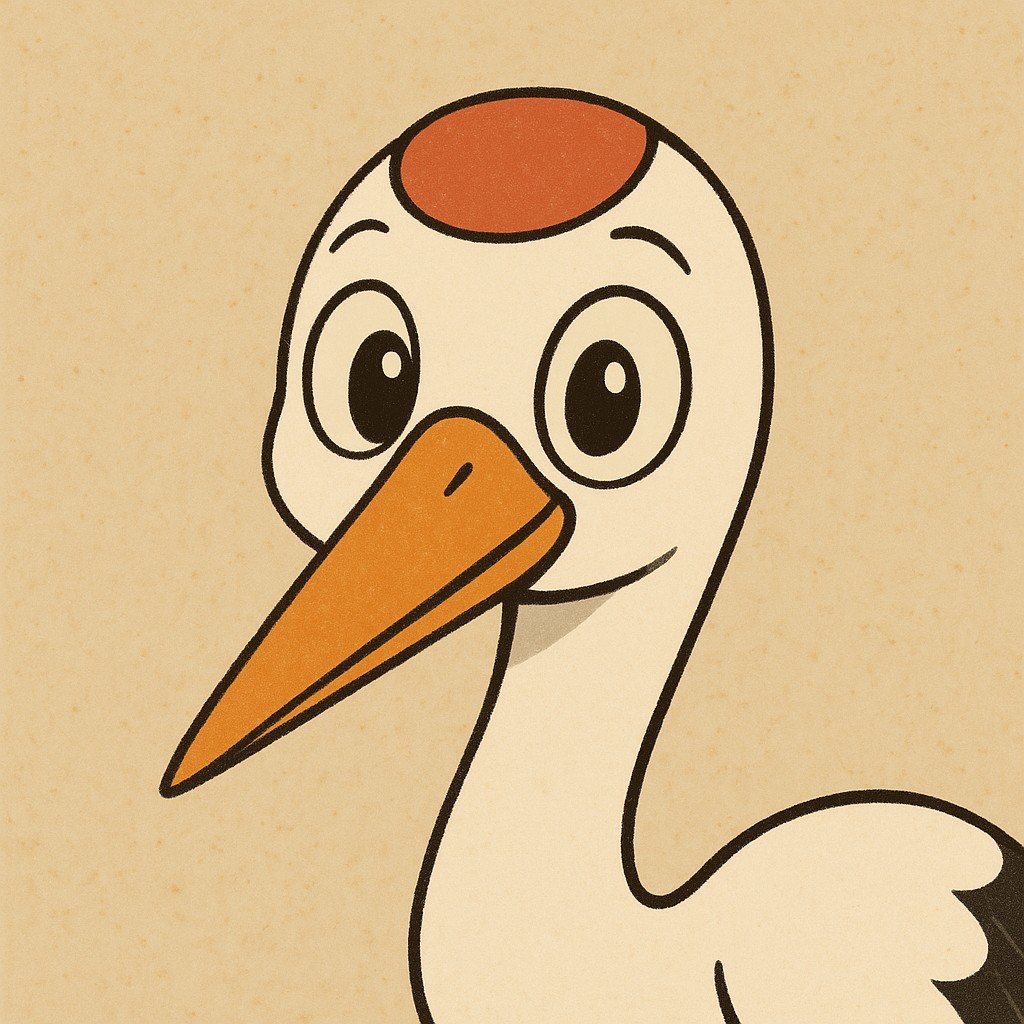
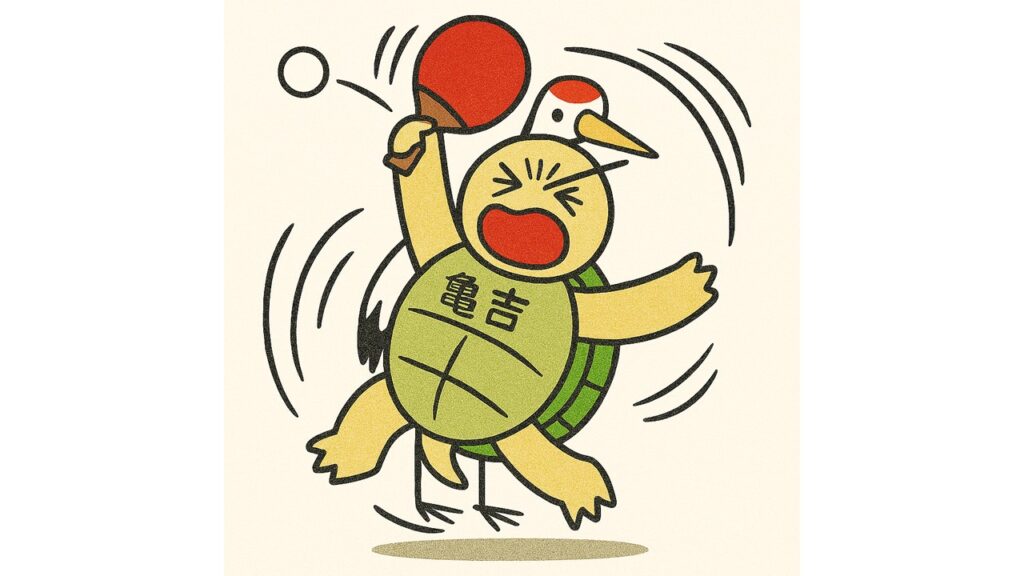
う~~ん。やる気じゃなくて、空間認知力が足りないんだなと思えば腹立たないか・・・。
3.動作表現力
もし、見たことのある運動を全く同じように動作ができたとしたらどうでしょうか?
指導者としては、こんな優秀な生徒さんばかりだとしたら苦労しないですね。
でも、そうだとしたら運動系のスクールはやっていけないです。見て実行できるなら習いに行く必要がないからです。

とはいえ「初めてなのに何となくそれっぽい動きができる」とか「見たらなんとなくできちゃう」なんて人を身近で見てきたことは無いかな?

いますいます。運動神経いいなぁ!!って思いました。
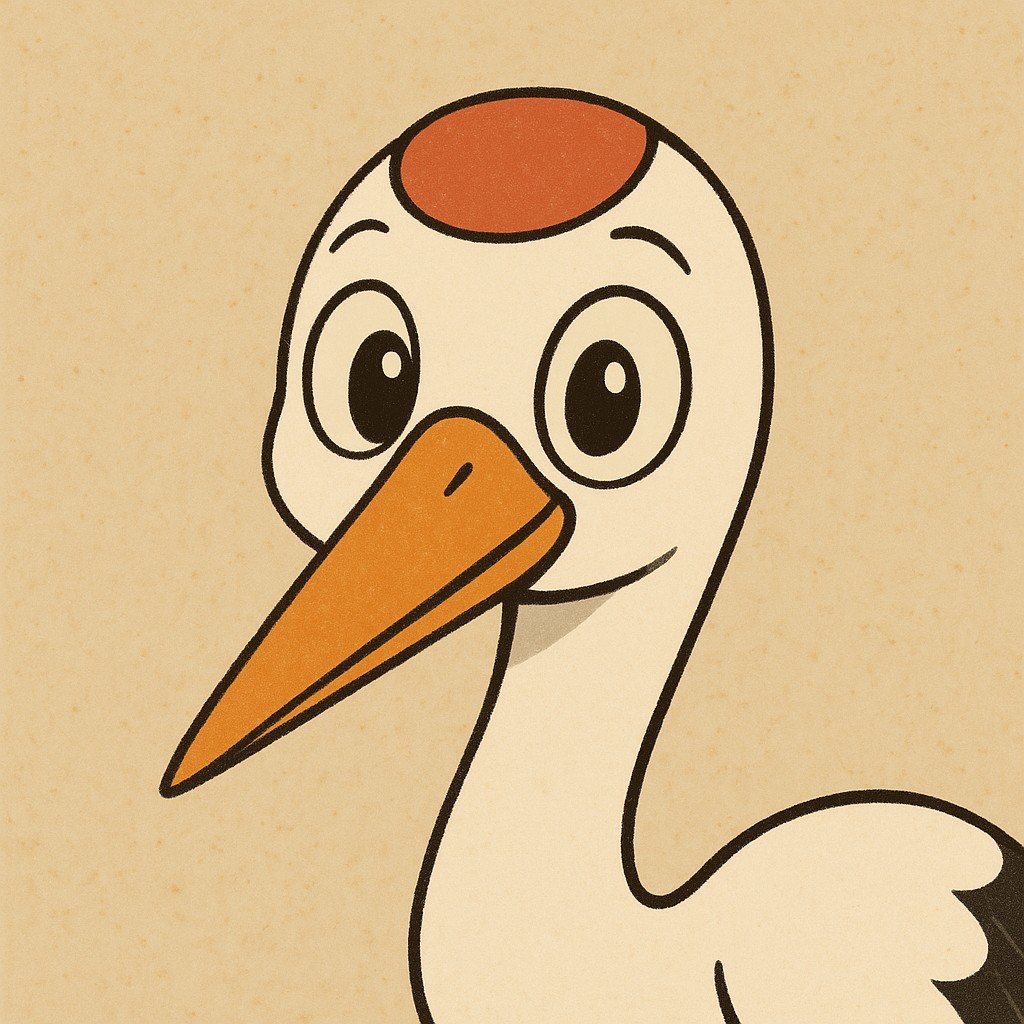
テレビでプロのダンサーが、ダンスチームに入ってすぐに踊れるようになってるのを見たことがあります。

ワシもダンスは得意だった。だから大概の運動はできたし自信もあった。
-683x1024.png)
この見たものを自分の体で表現できることを「動作表現力」と呼んでいるんだ。
3人の会話にあるように、プロのダンサー達がまさに動作表現力の高い人でなければ務まらない職業です。
生まれ持った才能もあるかもしれませんが、通常は、努力によって鏡の前に立って自分の動きを確認しながら地道な練習を繰り返すものです。しかし、この運動動作再現力が高い場合、全く新しい技術を習得しようと思ったときに、人よりも速くその動作を再現できる。スポーツをする際には大きな力となるのは間違いないです。
そして、この表現力には「再現する力」も含まれます。
例えば、ダーツの選手やボーリングの選手は、ほぼ同じ環境で同じ動作ができるからこそ的やピンを狙うことが可能です。過去に行った動きを寸分たがわず繰り返すことができる。
これを、動作『再現力』と呼んでいます。
4.基本フォーム力
基本という言葉と同意で使われるもに基礎があります。
この基本と基礎をスポーツにおいては、分けて考える必要があります。皆さんは、この違いを使い分けていますか?
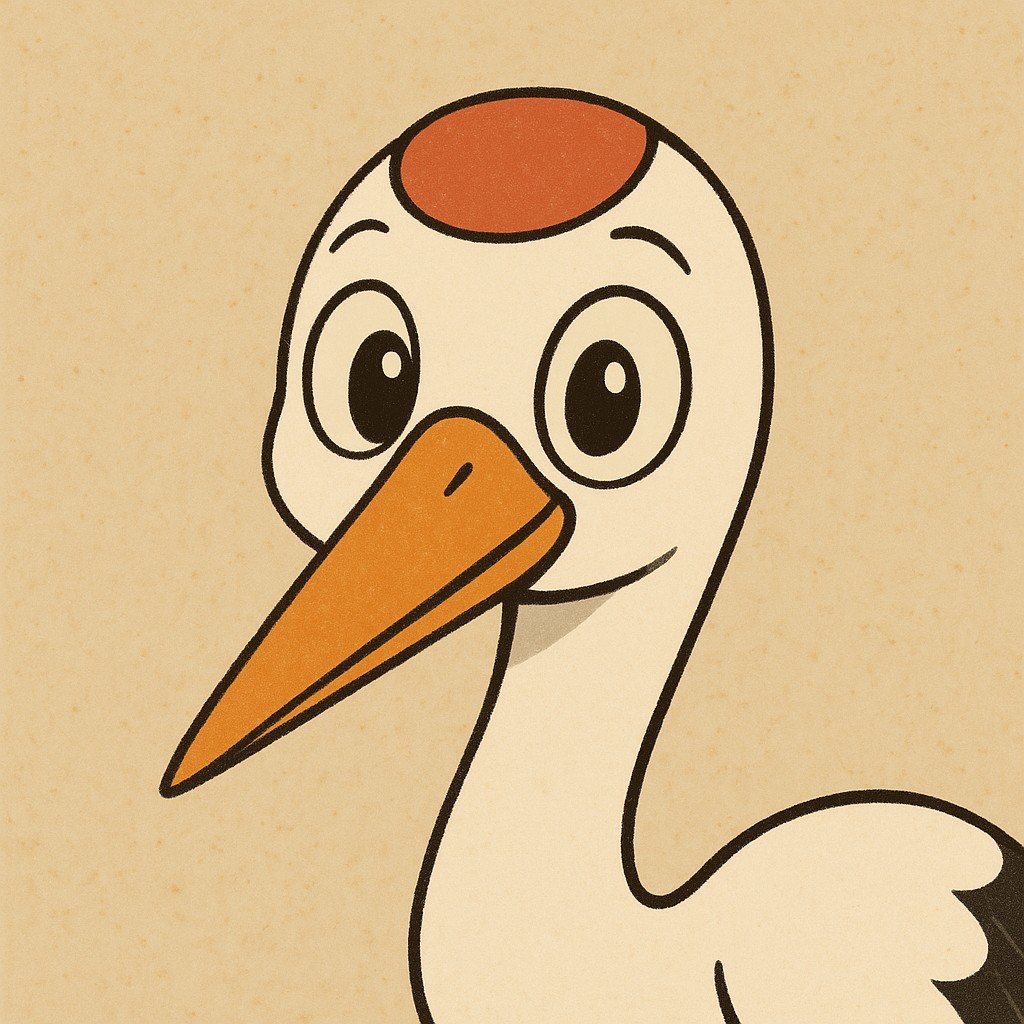
え!?基本と基礎は違うんですか?

そんなこと考えたこともないな~~~。違うんだ・・・

多くの人はそうだよね。
しかし、次の説明を聞くと納得いくはずだよ。
基礎:土台となる力や能力
基本:競技を行ううえで必要な技術の基となる動きや型
例えば、基礎には「走る、飛ぶ、投げる」といった動作を行ううえでの筋力や持久力など体力にかかわる要素で、どんなスポーツにおいても必要となる土台といえる。
そして、特定のスポーツにおいて応用的な動作や技を正しく安全に効率的にプレーするために身に着けておくべき技術習得が基本となります。
いわゆる、基本を行うためにも基礎(基礎体力)が必要となるといえます。
そのため、いくらスポーツ万能な方であっても、初めての競技を行うとしたら基礎はあっても基本は備わっていないといえるでしょう。

なるほど!!それならテニスを一所懸命練習して体力をつければ、基礎は成長させることができるけど、卓球の基本は身に着けることができないってことですね!!

お!!亀吉もだんだんと理解が早くなってきたね。成長しとる。
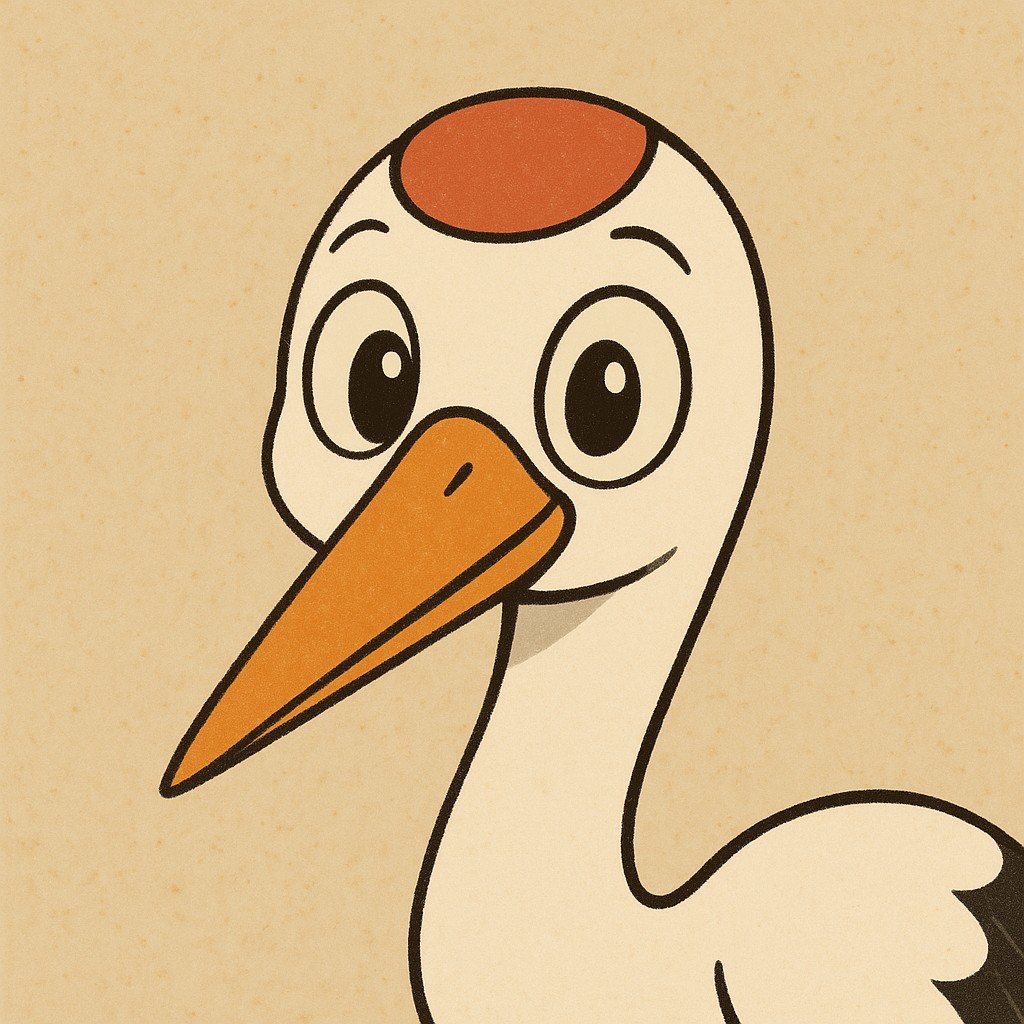
基礎と基本については分かったけど、改めて基本フォーム力って何ですか?
基本は、後に応用の技術の習得に重要であることは前述した通りです。
これを具体的な例として、シェークハンドのバックハンドロングで詳しくみてみましょう。
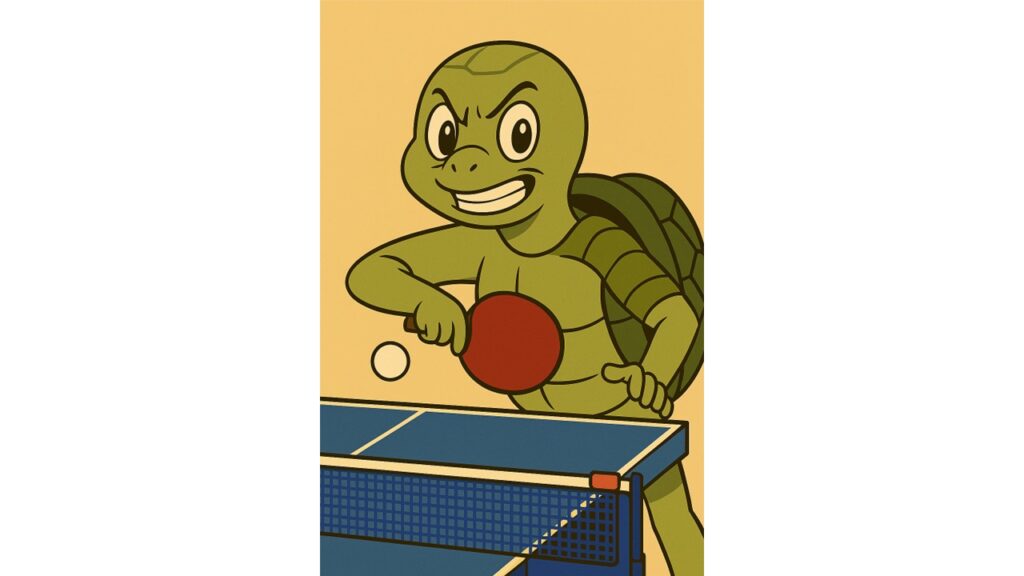
このバックハンドロングは、強く弾いて打球する「バックハンドスマッシュ」や回転を強くかける「バックハンドドライブ」。卓球台の上でドライブをかける「台上バックハンドドライブ」といった、相手に威力のあるボールを打ち込む応用技術に発展していきます。
いずれの打ち方もラケットを『体の正面から右斜め上方向に振る』必要があります。そのため、バックハンドロングの基本フォームもこれと同様にラケットが右斜め上方向に移動するスイングにならないといけません。
ただラケットが体の正面から前に『押し出す』打ち方で、バックハンドロングを初めに覚えてしまうと、後の応用技術の習得が難しくなります。
このように、応用技術に発展するラケットの動きを卓球を始めたばかり、いわゆるゆっくりとラリーが続けられる状態でも行っておくこと。そしてそのフォームを身に着けていることが『基本フォーム力』と言えます。
5.運動脳力
6アビリティーの1から4までは、目で見て分かる動作にかかわる「体」についてでした。ここからは見ることのできない「悩」の能力について解説していきましょう。

運動脳力という言葉を知っているかい?
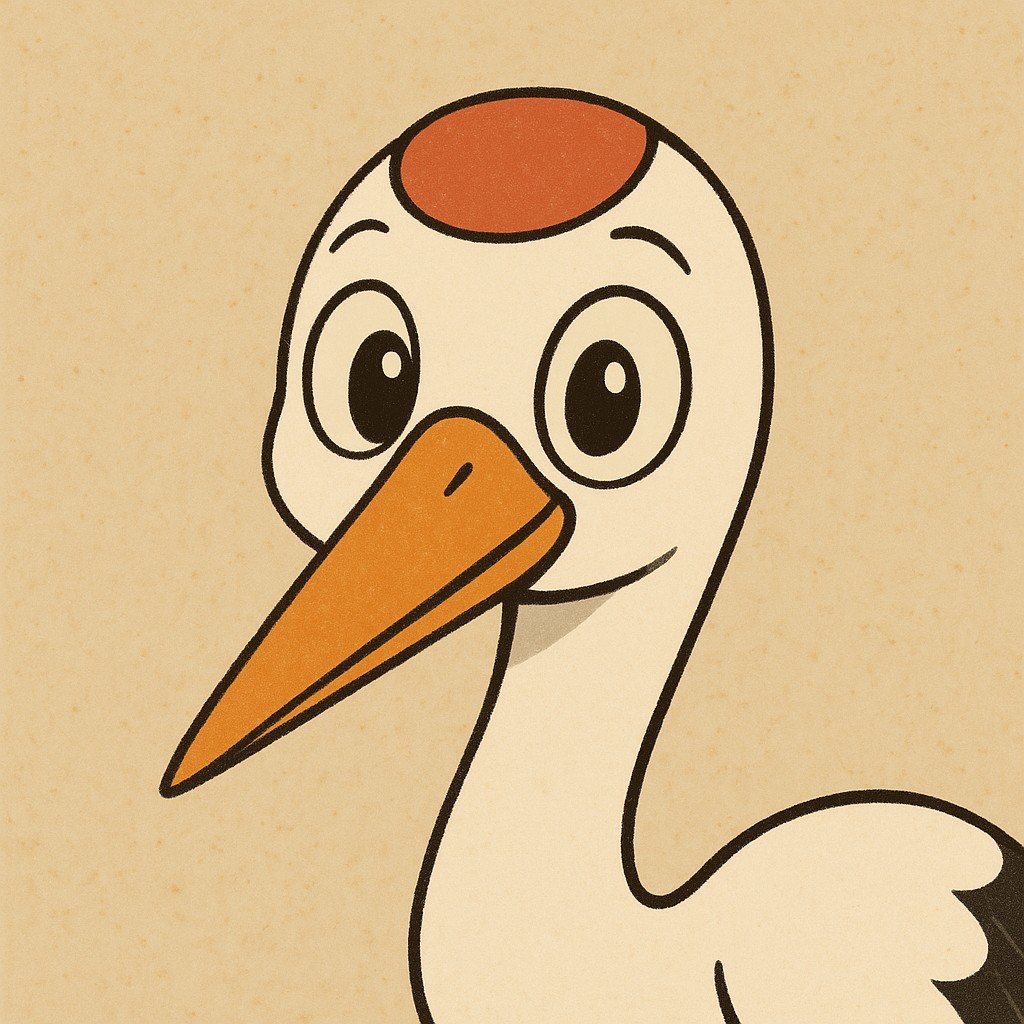
運動能力とはよく言いますけど・・。脳力!?は知らないです。

こんな感じでしょうか?
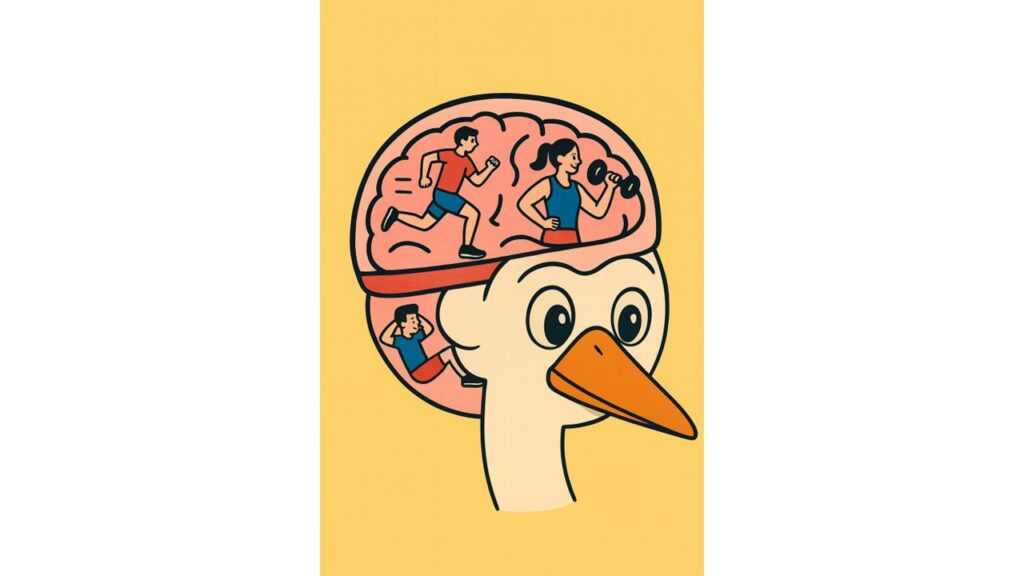
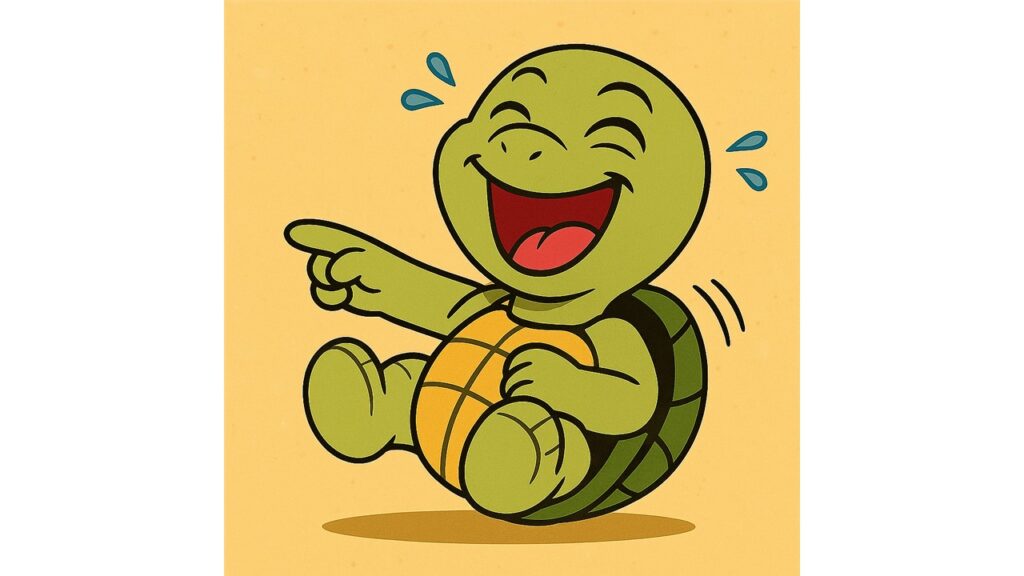

ははは(笑)。分かりやすいイラストありがとう。
知らなくて当然だ。これは私の造語だからね。2025年時点ではググってもでてこない。
皆さんも、当然聞いたことの無い言葉なのですが、これは6アビリティーの中でも非常に重要な運動を上達させる大切な能力の一つです。

ちなみに、運動をすると「悩」の働きがよくなる。運動をすると頭がよくなるといった研究や、それに関する書籍は書店でも多く目にする。でもそういった「スポーツすることはいい事ですよ!」といったものではないよ。
運動脳力とは「指導を受ける方がいままでにどれくらい運動に関する知識や経験をもち、指導者が伝える内容をどれくらい理解・イメージできるのかの能力」だよ。
実際に体を動かしているのを見ることができる「運動能力」は、高い・低い、できている・できていないが明確です。しかし、この「運動脳力」は、最終的には会話をしなければわからない力なのです。
具体的なたとえ話を一つ紹介します。
私が、Aさん、Bさん、Cさんという参加者に卓球の指導を行っていたとします。

「手の甲を上・下とひっくり返すときに、どこの関節を使ってますか?(私)」 実際にやってみる。
- Aさん:手首かなぁ・・
- Bさん:わかりません
- Cさん:前腕(肘から前の腕)です。

「ラケットでバックスピンをかけて壁にあててみます。このボールどうなるでしょう?(私)」
- Aさん:強く跳ね返る!!
- Bさん:わかりません
- Cさん:下に落ちて戻ってくる
さて、皆さんはAさん、Bさん、Cさんのうちどの方が運動脳力が高い方か分かりますか?
そうです。Cさんですね。
Cさんは体はどのように動いているのかが分かっていて、球技の経験や知識もあることが想像できます。
Aさんは、考えて答えをだそうという意欲はありますが、スポーツの経験はあまりない方で、イメージを言葉にしますが体がどのように動き、ボールに変化があった時にどんな状況が生まれるかを正確には分かっていないのです。
Bさんは、スポーツの経験がほとんどなく「私は運動苦手」と思っていて、考えても分からないとあきらめている状態です。
スポーツを上達させるには、脳が正しいイメージをもって自発的に「運動(自分の体を動かそうする)」をしなければなりません。
なぜ「自分はこれをやっているのか?何のためにこれを練習しているのか?」の状態では、指導者が離れた瞬間に再現性が低くなるわけです。
結果として、この3名に全く同じ時間、同じ内容の指導を行っても、残念ながらCさんだけが上達してしまうことになります。
上達には指導法だけでなく、受講者自身の力が大きく関わっています。ただし「受講者の力が足りないから無理」と言っているわけではありません。誤解しないでください。
ここで言う「脳力」は、鍛えられる能力(アビリティー)です。今は低くても、意識的に伸ばすことで技術習得のスピードが上がり、できる可能性も高まります。
よくある「運動すると脳から物質が出て記憶力が上がる」などの話とは違い、ランニングでスマッシュが上手くなるわけではありません。
しかし「運動脳力」を鍛えることで、運動を理解し、脳が「こう動かす」と指令を出せるようになります。私はその結果、技術習得が早まる例を何度も見てきました。そしてこの力は、特定の技術だけでなく、全体の上達に良い影響を与えるのです。
つまり「脳を鍛えるには運動しかない」ではなく、「脳を鍛えれば運動ができる」という考え方なのです。
6.運動学習力
「生徒がやる気を起こさないのは、指導者の力不足だ」と言われることがあります。
指導者が分かりやすい説明ができていない、生徒さんを引き付けられる話し方をしていない。といった生徒さんのパフォーマンスが上がらない原因は指導者側にありとする考え方です。

学校の勉強でも、先生によって楽しくって分かりやすい時とそうじゃない時があったなぁ~~

誰もが、こういった経験をもっているよね。
楽しかった授業もあれば、つまらない・嫌だと思った習い事もある。それを指導者によるものととらえがちだよね。。
確かに優れた指導者のもとで生徒が劇的に成長する例もあるけれど、趣味や自主参加型の学びでは受講者側に課題があることも多いんだ。
私が実際に体験した過去の事例に英会話スクールがあります。
大手のスクールで講師の方々は明るくフレンドリーな人ばかりでした。できるだけレッスンの中で日本語を使わないようにする方針だったのか、日本人の講師であっても受講者が全くの初心者に対しても英語だけで説明しようとしていました。
とあるクラスで中年の男性サラリーマンが参加していました。その方は口癖のように「分からない、分からない」と言っていて、すぐに諦めて日本語で聞き返し、周りの受講生にも日本語で質問をするなど学習環境を乱していました。それでも講師は笑顔を作ってジェスチャーを交えて頑張っていました。
毎度そのような状況でしたが、しばらくすると姿を見ることはなくなりました。当然、英語が上達しないままだったわけですが、明らかにこれは彼自身に問題があったはずです。

英語の勉強だから、僕でもそうなるかもなぁ~~。
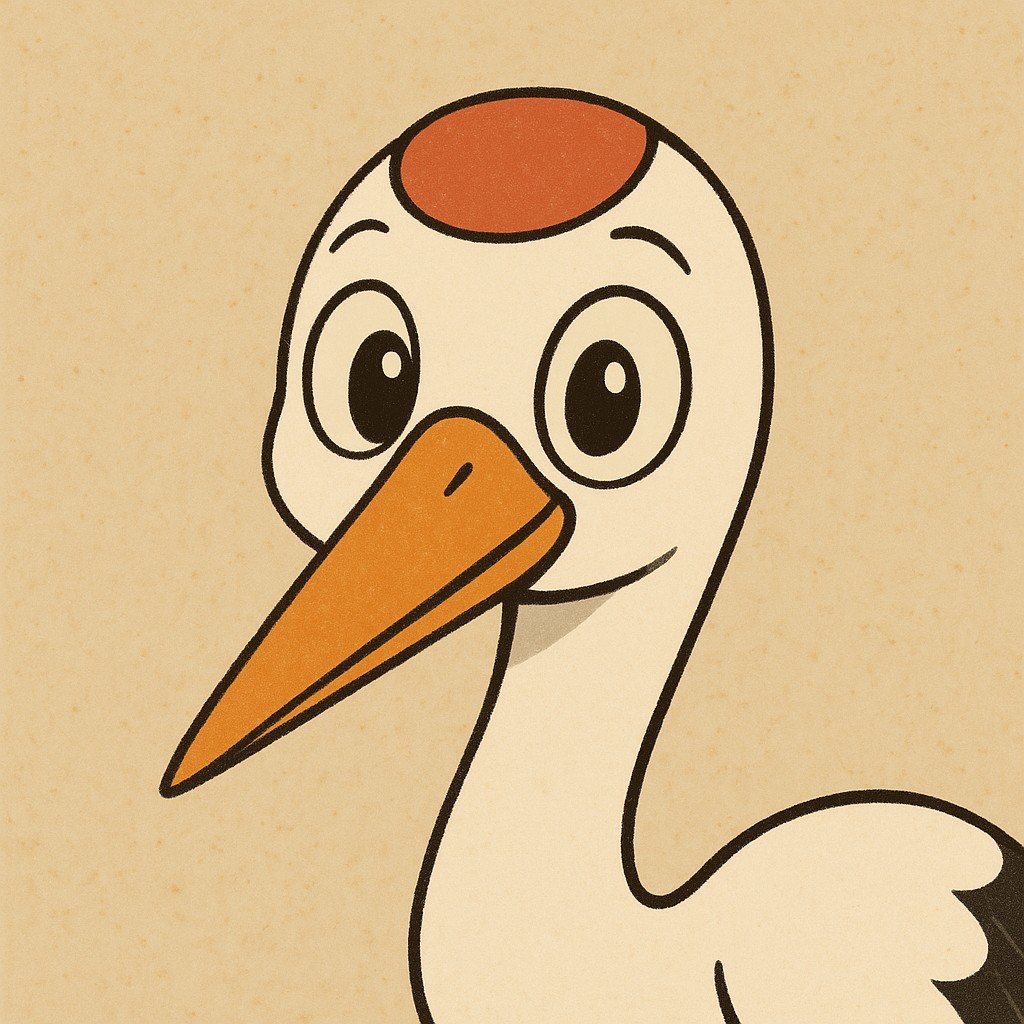
確かに「勉強」ってなると、そもそもやる気だすの難しいですよ。

うん。たとえ話として英会話スクールををあげたけれど、「運動をする」ことだって、体を使って『脳』がその動きを勉強している。と捉えれば全く同じことが言えないかな?
私は多くの方を卓球指導した経験から、運動の上達には「学ぼうとする姿勢」が不可欠だと実感しています。これは性格や過去の経験に左右されるもので一般的には「やる気」と捉えられます。これが低い人は上達は遅く指導者が無理に伸ばすのは困難です。
さきほどの英会話スクールの男性と同じように、今までやったことのないレベルの高い技術を教えようとしたときに、「無理、分からない、できない」とやる前から怖気づいてしまう方は沢山います。何とかトライしてもらっても、『ようし!私ならできる。頑張ろう』と思ってやろうとする方との上達の差はどうしてもでてしまうものです。
そして、これは心の中で起こっていることで外部で見学をしている方には全く分かりません。なので、「指導者がその気にさせていない」と判断してしまうわけです。
ただし、これは運動に限った話であり、他の分野で優れている人も多くいます。例えば弁護士やお医者さん、学校の先生であっても運動となったら「私のやり方でやる」と言って、指導者のアドバイスに耳を傾けないケースもあります。これも学ぶ上では障害となるため上達が遅くなります。
このように、単に「やる気」だけを指すわけではないので『運動学習力』と呼ぶようにしています。そして、この運動学習力を高めるのは、他の能力と同様に成長させるには時間がかかり、大人はもう変えられないケースも多く、それを無理に変えようと接すればすぐに辞めてしまいます。

だからといって全て生徒が悪く指導者は頑張らなくてよいと言っているわけでは無いんだ。
むしろ逆で、やる気がないと考えずに「やる気を出すことができない=まだ運動学習力が低い」と捉えて、どうやったらその能力を高められるんだろう。その力が低いひとにはこういうアプローチをした方が受け入れやすいんではないか。と指導者が冷静に判断をしながら長期的な目線で工夫をこらすことが大事なんだ。
大切なのは、受講者との距離感を見極め、無理のない関係性を築くこと。運動学習力が低い人には、言葉での説明よりもプレーを楽しませる時間を増やすことで、自然と力が伸びていく可能性もあります。
子供はまだ自分の目的を理解していないことも多く、ふざけたり集中できない場面もあります。それでも、成功体験を積み重ねることで「できる自分」を認識し、運動学習力が高まっていきます。
この経験は、子供にとって生きる力を育む貴重なもの。だからこそ、子供時代に運動をすることには大きな意味があると私は考えています。

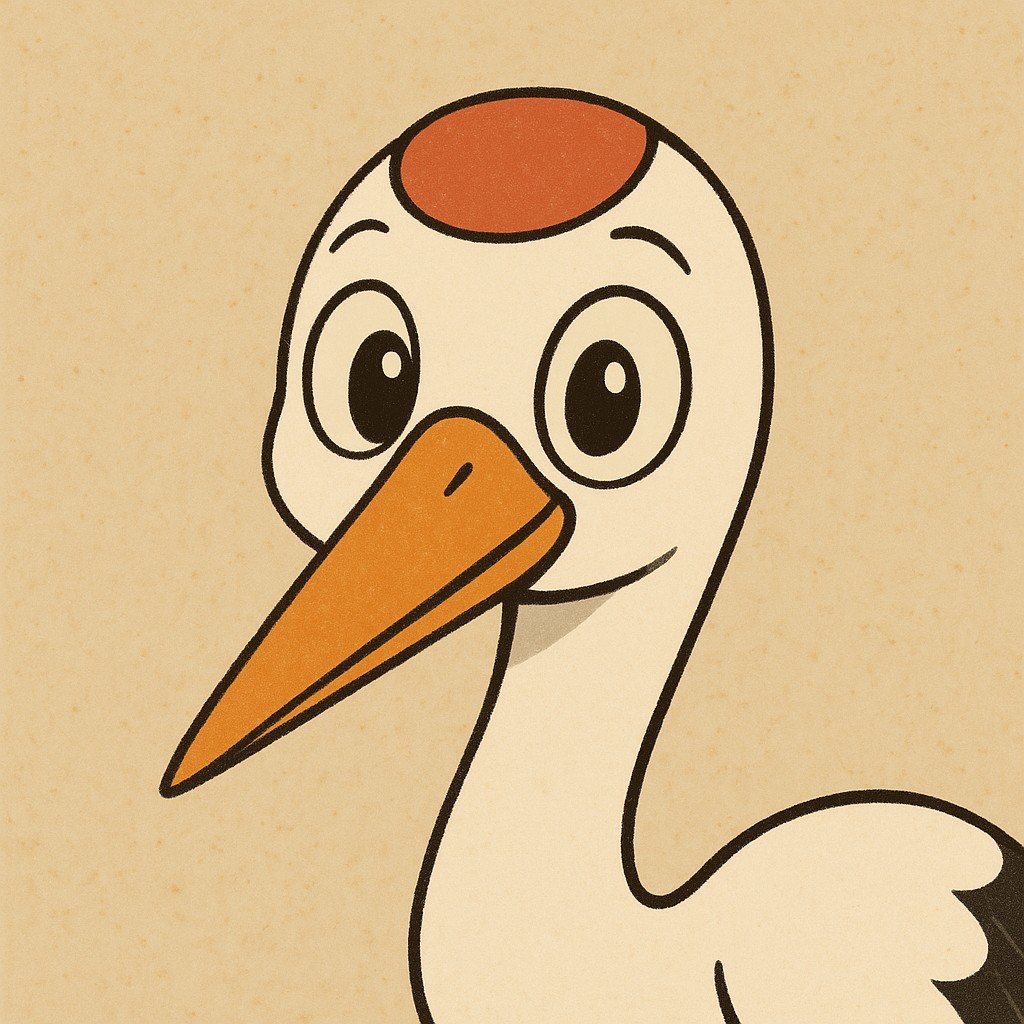
いやいや、キャラ崩壊してるがな。